2024年度 東京支部 技術セミナー開催報告
「避難を支える光」セミナー報告
照明学会東京支部では、照明に関する最新の技術や課題について専門家を招いた技術セミナーを定期的に開催しています。今回は「避難を支える光」をテーマに、水害や地震などの広域災害時における避難行動、心理的影響、空間認識に基づいた照明デザインについて議論が行われました。
開催概要
- 日時:2025年3月13日(木) 14:00~16:30
- 会場:連合会館 201会議室
- 参加者:33名
実施内容
1.趣旨説明
セミナーの司会は篠原副支部長が務めました。冒頭では小林支部長が趣旨説明を行い、特に津波や洪水など長距離移動を伴う避難において、適切な照明が不可欠であることを指摘しました。
2. 小林茂雄氏(東京都市大学)
小林氏は、2020年に設立された「災害に備えたレジリエントな屋外照明研究調査委員会」の取り組みを紹介しました。正常性バイアスや空間認知の歪みが避難行動に与える影響について説明し、都市計画における空間認知の概念を応用しながら、釜石市や気仙沼市での社会実験を基に、低輝度でも効果的な避難照明の配置方法を提案しました。
3.秋月有紀氏(富山大学)
秋月氏は、災害時の屋外照明の基準・技術・課題について講演しました。JIS基準には防災照明に関する明確な規定がなく、避難経路の床面照度や避難誘導灯の有効性の検討が必要であると指摘しました。また、山口県長門湯本温泉や南あわじ市福良地区での事例を紹介し、視認性向上のための照明調査や仕様改良の取り組みについて説明しました。さらに、レジリエント照明の国際的な取り組みについても紹介がありました。
4.角舘政英氏(ぼんぼり光環境計画)
角舘氏は、平時と災害時の両方に対応した照明デザインの実例を紹介しました。岩手県釜石市では、高台避難を促すために階段や坂道を光で可視化する手法を検証し、市内全域に展開。宮城県気仙沼市では、公園や道路、防潮堤の照明計画を統合し、広域避難を支援する取り組みが行われました。また、茨城県大洗町では、観光と避難誘導照明を融合させる試みが紹介されました。さらに、危険予測を踏まえた交差点照明の考え方についても言及しました。
5.パネルディスカッション
講演後、登壇者3名によるパネルディスカッションが行われ、避難照明のあり方について活発な意見交換がなされました。
6.閉会の挨拶
最後に、藤田事業企画委員長が講師と参加者へ謝辞を述べ、セミナーは終了しました。
本セミナーを通じて、災害時の避難を支援する照明の重要性や今後の課題について理解を深める機会となりました。
≪セミナーの様子≫

開会

講師の小林様
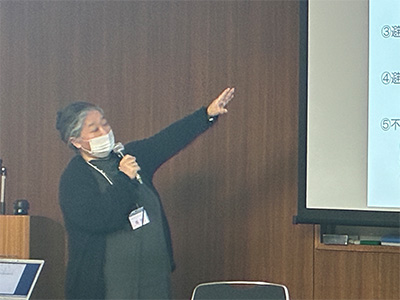
講師の秋月様

講師の角舘様

パネルディスカッション

質疑応答
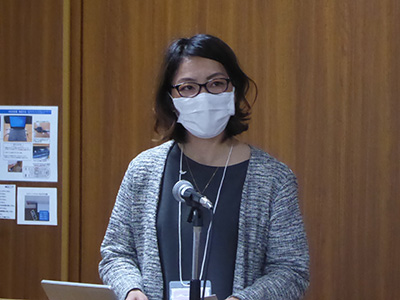
司会 篠原副支部長

閉会挨拶 藤田事業企画委員長

